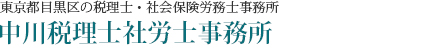
ご対応エリア:東京都全域・23区(目黒区、港区、中央区、千代田区、
品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区他)、神奈川県、埼玉県、千葉県など
受付時間:9:30~17:30(土日祝祭日は除く)
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
03-6455-1620
被保険者となる人
どのような人が社会保険・労働保険の被保険者になりますか?
被保険者となるべき者は制度によって異なります。
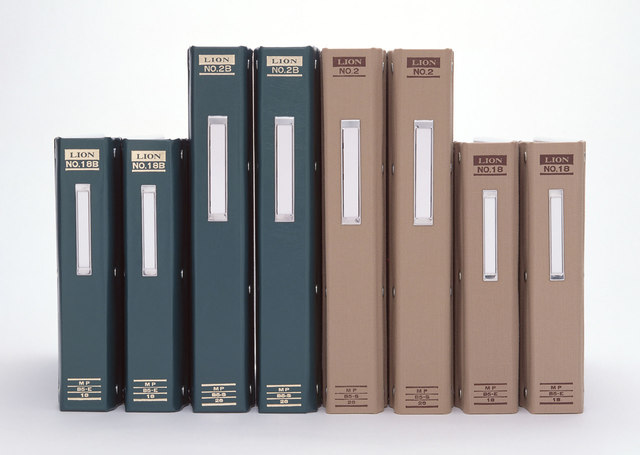
1. 健康保険(協会けんぽ、健保組合)・厚生年金保険
適用事業所に常時使用される75歳未満(厚生年金保険は70歳未満)の者は被保険者となります。適用事業所とは、常時従業員を使用する法人の事業所や常時5人以上の従業員を使用する一定の事業所をいいます。法人の事業所は1人でも適用対象となる役員、従業員がいれば適用事業所となります。
正社員は当然被保険者となりますが、パートタイマー等については次の通りとなります。
(1) パートタイマー
次のa、bのいずれも満たす場合には常用の使用関係にあるものとして被保険者となります。
a.1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること
b.1カ月の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること
(2) アルバイト
アルバイトなど臨時に雇用される者で、次に該当する場合は、原則として被保険者となりません。
a. 日々雇い入れられる者。ただし、1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、1カ月を超えたときから被保険者となります。
b. 2カ月以内の期間を定めて使用される者。ただし所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった場合には超えたときから被保険者となります。
c. 4カ月以内の季節的業務の使用される者。ただし、当初から4カ月を超え引き続き使用される予定の場合は当初から被保険者となります。
d. 臨時的業務の事業所に使用される者。ただし、当初から6カ月を超え引き続き使用される予定の場合は当初から被保険者となります。
なお、上記a~bの期間は日雇特例被保険者の適用を受けることができる場合があります。
2. 雇用保険
労働者を1人でも使用している事業所は、国の直轄事業や一定の農林水産業等を除き、原則として強制的に適用事業所となります。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者は、原則として雇用保険の被保険者となります。ただし、一定の者については適用除外となります。
3. 労災保険
労働者を1人でも使用している事業所は、国の直轄事業や一定の農林水産業等を除き、原則として強制的に適用事業所となります。
被保険者となる者は、正社員だけでなく、アルバイト、パートタイマー、日雇労働者、外国人など労働時間の長短、就業形態、国籍などにかかわらず、すべての労働者が対象となります。代表権、業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりませんが、一定の場合には特別加入制度により労災保険の適用を受けることができます。
社会保険・労働保険の保険料は誰が負担するのでしょうか?
労災保険料は事業主が全額負担しますが、その他の制度は、原則として被保険者と事業主が負担します。

1. 健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険
標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じて保険料を求めますが、原則として、被保険者と事業主で折半して負担します。
厚生年金保険料の料率は全国一律で18.3%(平成29年9月~)ですが、これを折半しますので、被保険者と事業主の負担は各9.15%となります。また、健康保険料(協会けんぽ)の料率は都道府県によって異なり、例えば東京都は9.98%(令和6年3月~令和7年2月分、毎年3月分から改定)ですが、これも労使折半します(東京都の場合、折半すると各4.99%)。なお、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者については、健康保険料と一緒に介護保険料(1.60%、折半0.80%)も徴収され、介護保険料も折半となります。
ただし、児童手当拠出金については、被保険者から徴収されず、事業主のみの負担となります。
2. 雇用保険
一般の事業の場合、雇用保険料率は1.55%(令和6年度)となり、そのうち雇用保険二事業の保険料率(0.35%)は事業主の負担となりますが、それ以外の失業等給付に係る保険料率0.60%は被保険者と労働者で折半して負担します。
つまり、事業主負担は0.95%、被保険者負担は0.6%となります。
協会けんぽの任意継続被保険者制度について教えてください。
任意継続被保険者の概要は次のとおりです。

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、一定条件のもとに本人の希望により退職前の制度に継続して被保険者となることができます。任意継続被保険者となるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1) 資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間がある。
(2) 原則として、資格喪失日から20日以内に被保険者となるための届出をする。
任意継続被保険者となることができる期間は、原則として2年間ですが、次に該当する場合には、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を喪失します。
a. 死亡したとき〈翌日〉
b. 正当な理由があると認められた場合を除き、保険料納付期日までに保険料を納付しないとき〈翌日〉
c. 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき〈その日〉
d. 船員保険の被保険者となったとき〈その日〉
e. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき〈その日〉
保険料は全額被保険者負担です。
保険料率については、在職者の場合と同様に都道府県ごとに異なる率が適用され、40歳以上64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する場合には介護保険料も上乗せして徴収されます。任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均額30万円のいずれか低い方が適用されます。 定年退職等の場合は、一般的に退職時の標準報酬月額が高いため、全被保険者の平均額30万円が適用されることが多いです(健保組合の場合、組合によって平均額が異なります。)。また、60歳未満の場合、国民年金にも加入しなければなりませんので注意が必要です。
なお、退職者の場合、住所地の国民健康保険に加入するという選択肢もありますが、国民健康保険の保険料を概算で算定し、いずれか低い方の制度に加入することが多いようです。
協会けんぽの被扶養者の範囲はどのようになっていますか?
一定の親族等が被扶養者となります。

健康保険では被保険者の被扶養者についても保険給付が行われます。被扶養者の範囲は次のとおりです(後期高齢者医療制度の被保険者等を除く)。
1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含みます)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
<生計維持の基準について>
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、原則として、以下の基準により判断します。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には被扶養者となります。
標準報酬月額とは何でしょうか?
社会保険料や保険給付の額の計算の基礎となるもので、給料等の月額を基に計算します。

健康保険(介護保険第2号被保険者を含む)、厚生年金保険では、被保険者が事業主から支払を受ける報酬(賃金、給料、俸給、手当など被保険者が労務の対象として受けるものすべて)の月額を区切りのよい幅で区分して標準報酬月額を設定します。なお、年3回以下の賞与は標準賞与額とされます。
標準報酬月額は、健康保険は第1級5万8千円から第50級の139万円までの全50等級、厚生年金保険は第1級8万8千円から第31級62万円の全31等級に区分されています。
標準報酬月額の決め方には、育児休業等の改定を除き、次の3種類があります。
1. 資格取得時の決定
資格取得時の報酬の月額を基に決定します。
2. 定時決定
7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、報酬の支払基礎日数が17日未満の月は除外して計算します。
3. 随時改定
標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額に著しい変動が生じた場合には、標準報酬月額の改定を行うこととされており、これを随時改定といいます。改定された標準報酬月額は次の定時決定までの標準報酬月額となります。随時改定は次の3つすべてに当てはまる場合に固定的賃金の変動があった月から4カ月目に改定が行われます。
- 昇(降)給などで、固定的賃金(基本給、諸手当で月単位等で一定額が継続して支給されるもの)に変動があったとき
- 固定的賃金の変動月以後継続した3カ月間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
- 3カ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
例えば、10月支給の給与から固定的賃金の変動があり、上記の要件を満たす場合には、4カ月目である翌年1月分保険料から改定されますので、実際には5カ月目である翌年2月支給の給与から徴収する保険料から変更されます(当月分の保険料は翌月支給の給与から徴収されるため)。
ボーナスからも社会保険料は徴収されますか?
標準賞与額に料率を乗じて計算した保険料が徴収されます。

平成15年4月に導入された「総報酬制」により、標準賞与額に対しても標準報酬月額と同様の料率が適用され社会保険料が計算されます。標準賞与額とは、被保険者期間中に実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額をいい、賞与が支給される月毎に決定されます。
標準賞与額に含まれる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、被保険者が労務の対象として支払を受けるすべてのもののうち年3回以下のものをいいます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。
賞与を支給した場合には、支給日から5日以内に賞与支払届を、所轄年金事務所に提出する必要があります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1カ月当たり150万円が上限となります。
例えば、夏と冬の年2回の賞与が支給される会社で、夏200万円、冬200万円の賞与の支給がされた人の保険料は次のようになります。
<健康保険>
夏200万円+冬200万円=400万円≦上限540万円
∴夏冬共に200万円×料率
<厚生年金保険>
夏 200万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率
冬 200万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率
健康保険の給付(出産に関するもの)
出産に関する健康保険(協会けんぽ)の給付にはどのようなものがありますか?
出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手当金があります。

1. 出産育児一時金(家族出産育児一時金)
出産育児一時金(被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金)は、被保険者または被扶養者が出産した場合に、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円)が支給されるものです。
健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の出産、死産、流産、人工妊娠中絶、早産をいいます。
出産育児一時金は、原則として、被保険者が出産した場合に支給されますが、被保険者の資格を喪失してから6カ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には支給されます。
現在では、直接支払制度や受取代理制度が制度化され、窓口での負担軽減が図られています。
2. 出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、事業主から給与を受けられない場合には、出産日(出産日が予定日よりも遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲内で出産手当金が支給されます。出産日が予定日よりも遅れた場合は出産予定日以前42日からとされていますので、遅れた日数分も支給されるということになります。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額とされますが、会社を休んだ期間について事業主から給与の支給を受けられる場合は、その給与の額を控除した金額が支給されます。
なお、任意継続被保険者に対しては、原則として出産手当金は支給されないこととされています。
お問合せはこちら
事務所案内
中川税理士社労士事務所
代表者
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
住所
東京都目黒区青葉台3-10-1
VORT青葉台Ⅱ 7階
03-6455-1620
03-6455-1621
受付時間:9:30~17:30


