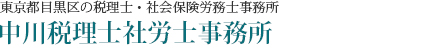
ご対応エリア:東京都全域・23区(目黒区、港区、中央区、千代田区、
品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区他)、神奈川県、埼玉県、千葉県など
受付時間:9:30~17:30(土日祝祭日は除く)
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
03-6455-1620
会社の決算上の利益が法人税計算上の課税所得金額となるのでしょうか?
会社の決算上の利益を出発点として、法人税上の調整を加えて所得金額を計算します。
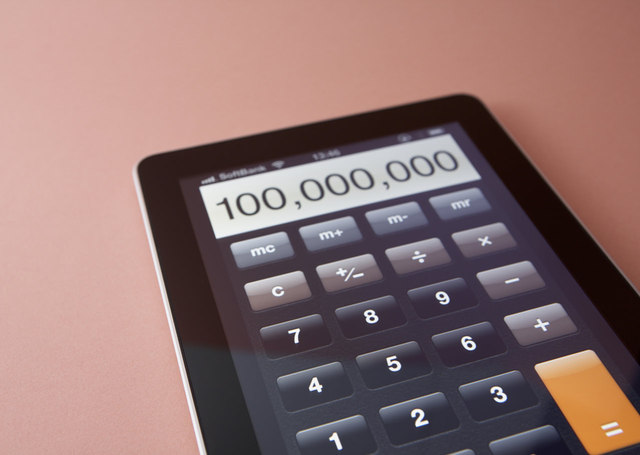
法人税の課税所得は、益金の額から損金の額を控除して計算しますが、実際には益金の額から損金の額を控除して計算するのではなく、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整(加算、減算)して法人税の課税所得を計算します。
これら調整計算は、法人税申告書の別表四において行いますので、別表四を見ればどのような加減算が行われているかわかります。一般的は(4)の損金不算入項目が多いかと思います。
(1) 企業会計の収益であるが、益金とならないもの(益金不算入)…減算項目
(2) 企業会計の費用・損失ではないが、損金となるもの(損金算入)…減算項目
(3) 企業会計の収益ではないが、益金となるもの(益金算入)…加算項目
(4) 企業会計の費用・損失ではあるが、損金とならないもの(損金不算入)…加算項目
売上の計上時期
売上はいつ計上する必要があるのでしょうか?
法人税法上の役員は会社法等に定める役員と同じでしょうか?
法人税法上における役員は、会社法等における役員の範囲よりも広くなります。

1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2. 1以外の者で次のいずれかに該当するもの
(1) 法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(例)取締役、理事とはなっていない総裁、副総裁、会長、副会長、相談役、顧問など
(2) 同族会社の使用人のうち、次のすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
イ) その会社の株主グループを株式等の所有割合の大きいものから順位を付した場合において、次のいずれかの株主グループに属していること
- 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合のその第1順位の株主グループ
- 第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計すると、初めて50%超となる場合のその第1順位と第2順位の株主グループ
- 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計すると、初めて50%超となる場合のその第1順位から第3順位までの株主グループ
ロ) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
ハ) その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること
上記2は 会社法等に定める役員ではありませんが、法人税法では役員の範囲に含まれます。したがいまして、登記上、取締役等でない場合でも、法人税法においては役員となる場合がありますので、役員給与や役員退職金の支給など注意を要する必要があります。
役員給与
法人が役員に支給する給与は全額損金の額に算入されるのでしょうか?
一定のものを除き、損金不算入とされます。

法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれかに該当すれば、原則として損金の額に算入されますが、該当しないものは損金の額に算入されません。また、これらの給与に該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされます。
(注)退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人分給与、仮装・隠ぺいして支給するものを除きます。
1. 定期同額給与
定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その支給時期における支給額が同額であるものをいいます。毎月同額支給する役員給与が該当します。なお、次に掲げる改定が行われた場合で、改定前の各支給時期の給与が同額で、かつ、改定後の各支給時期の給与の額が同額である場合も定期同額給与に該当します。
- 原則として、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに行われる改定(定時株主総会において行われる通常の改定)
- 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等による改定(臨時改定事由)
- 経営状況が著しく悪化したこと等による改定(業績悪化改定事由)
また、継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される額が毎月おおむね一定であるものも定期同額給与に該当します。
2. 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与(定期同額給与および利益連動給与に該当するものを除きます)をいいます。この給与に該当すれば、上記1に該当するもの以外でも損金算入することができますが、原則として事前に届け出た時期に届け出た金額を支給する必要があります。
3. 利益連動給与
同族会社以外の法人が、業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益等に関する指標を基礎として算定される給与)で一定の要件を満たすものをいいます。
交際費等の損金不算入
法人が交際費を支出した場合には損金の額に算入されるのでしょうか?
原則として損金の額に算入されませんが、中小法人については、一定の限度額までは損金として認められます。

法人税上の交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用、カレンダー、手帳、うちわなどの贈答費用、会議の茶菓・弁当代などは交際費等から除かれています。また、1人当たり10,000円以下の得意先等との一定の飲食費についても交際費等から除かれています。
交際費等については、中小法人を含む全法人(期末資本金100億円超の法人を除く)について、飲食のために支出する費用の額(※)の50%相当額を損金の額に算入できます。期末資本金の額が1億円以下の中小法人については、年800万円の定額控除限度額との選択適用になります。
※専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる「社内接待費」)を除きます。
法人が納付する租税公課は損金の額に算入されますか?
原則として損金の額に算入されますが、損金不算入とされるものもあります。

租税公課は法律に基づいて強制的に賦課徴収されるものですので、法人の事業遂行のために必要な費用と考えられます。法人税法では、租税公課は原則として損金の額に算入されますが、損金不算入とされるものもあります。
1.損金不算入とされる租税公課
(1)法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
→所得に対して課税されるものであるため
(2)各種加算税、加算金、延滞税、延滞金(納期限の延長に係るものを除く)ならびに過怠税
→ペナルティ的なものであるため
(3)罰金および科料ならびに過料
→同上
(4)法人税から控除する所得税および外国法人税
→税額控除を選択するため
2.租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期は次のとおりです。
(1)申告納税方式(酒税、事業税、事業所税など)
原則として、納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入されます。
(2)賦課課税方式(不動産取得税、固定資産税、自動車税など)
原則として、賦課決定のあった事業年度の損金の額に算入されます。
(3)特別徴収方式(ゴルフ場利用税、軽油引取税など)
原則として、納入申告書を提出した事業年度の損金の額に算入されます。
(4)利子税、納期限の延長に係る延滞金
法人が寄附金を支出した場合には損金の額に算入されるのでしょうか?
原則として、一定限度内の損金算入が認められています。

寄附金は事業との関連性が明確でないため、国等に対する寄附金など公益的な性格を持つものを除いて、一定限度内の損金算入しか認められていません。また、法人による完全支配関係(100%支配関係)にある内国法人間で平成22年10月1日以後に支出した寄附金や国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入とされます。
(1)指定寄附金等(国、地方公共団体に対する寄附金、財務大臣の指定した寄附金)
→ 公益性が高く、全額損金算入
(2)特定公益増進法人等(特定公益増進法人、認定NPO法人)に対する寄附金
→ (3)とは別枠で一定限度内の損金算入
(3)一般の寄附金
→ 一定限度内の損金算入
資本または出資を有する普通法人等が支出した上記(2)、(3)の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。
<損金算入限度額>
上記(2)特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額=(所得基準額+資本基準額)×1/2
- 所得基準額=寄附金支出前の当期の所得金額 × 6.25%
- 資本基準額=期末資本金等の額 × 当期の月数/12 ×0. 375%
上記(3)一般の寄付金の損金算入限度額
損金算入限度額=(所得基準額+資本基準額)×1/4
取得価額が少額な減価償却資産についても定率法等により償却する必要がありますか?
一定の少額な減価償却資産については特例が認められています。

法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合には、原則として、定率法や定額法等により、法定耐用年数に渡って償却計算を行いますが、取得価額が少額な減価償却資産については、特例が設けられています。
(1) 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法人が事業の用に供した減価償却資産で使用可能期間が1年未満であるものまたは取得価額が10万円未満であるものを有する場合、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の損金の額に算入されます。取得価額全額を損金経理した場合に限りこの規定が適用されますが、定率法等により通常の償却計算を行うことや、下記(2)の方法によることもできます。
なお、所得税にも同様の規定が設けられていますが、所得税の場合は通常の償却方法や下記(2)は選択できず、取得価額全額を必要経費に算入することが強制されますので注意が必要です。
(2) 一括償却資産の損金算入
法人が事業の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(上記(1)の適用を受けるもの等を除く。以下「一括償却資産」という)を有する場合には、その一括償却資産の取得価額の合計額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額を損金の額に算入することができます。例えば、1年決算法人であれば、一括償却資産の取得価額の合計額に12/36を乗じて計算した金額が1事業年度の損金算入限度額となりますので、3年間で均等償却できることとなります。
なお、取得価額が20万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、一括償却資産とせず通常の償却方法(定率法など)により減価償却を行うことも可能です。
(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
青色申告者である中小企業者等(資本金1億円以下の普通法人等)が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得等し事業の用に供した減価償却資産で取得価額が30万円未満(一定のものを除く)であるものを有する場合において、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額を、その事業年度の損金の額に算入することができます。なお、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、この特例を適用せず、通常の償却方法(定率法など)を選択することも可能です。
この特例を適用する場合、1事業年度あたりの取得価額合計額が300万円(事業年度が1年未満の場合は月数按分)に達するまでが限度とされます。
また、上記(1)または(2)の適用を受ける減価償却資産は償却資産税の対象となりませんが、この特例を選択した減価償却資産については、償却資産税の対象とされるため注意が必要です。
お問合せはこちら
事務所案内
中川税理士社労士事務所
代表者
中川 幸治 (なかがわ こうじ)
住所
東京都目黒区青葉台3-10-1
VORT青葉台Ⅱ 7階
03-6455-1620
03-6455-1621
受付時間:9:30~17:30



